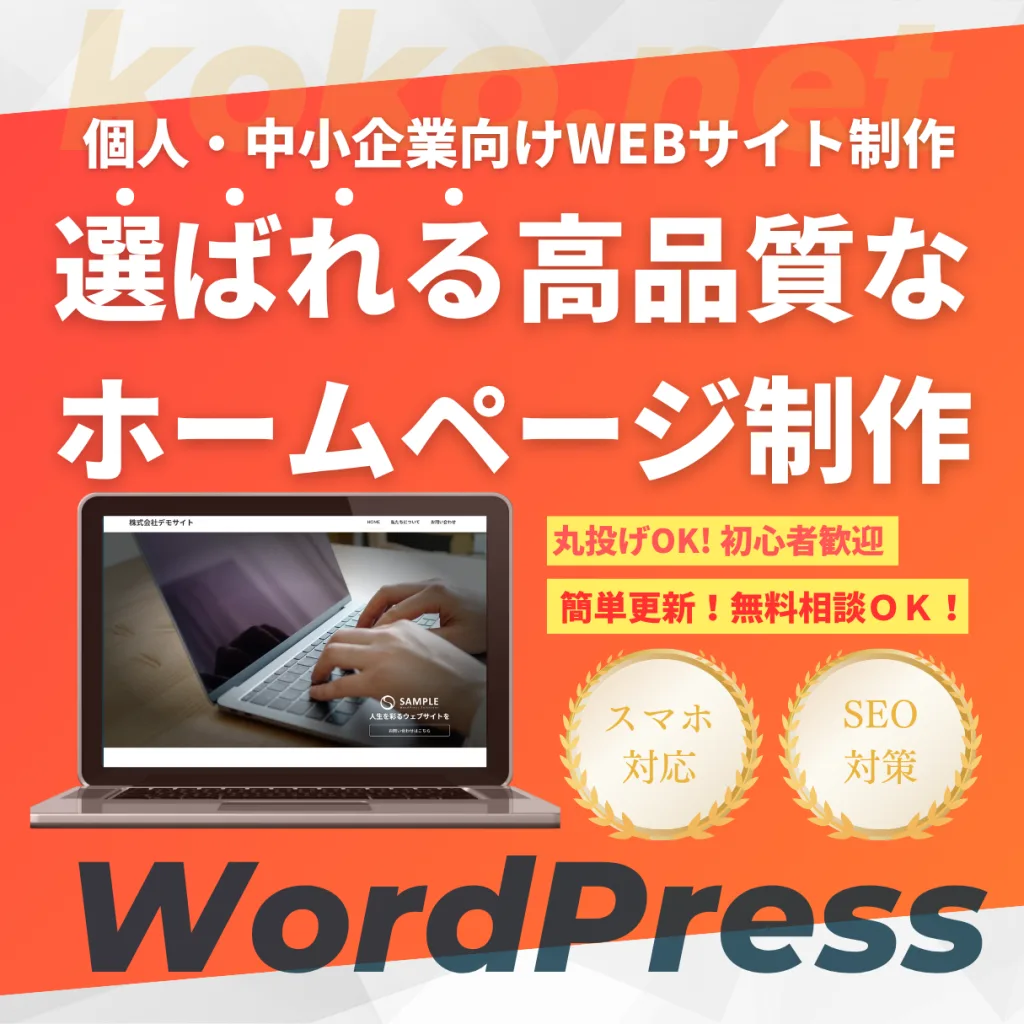個人と会社、どっちに頼むべき?Web制作を外注するときの判断基準

「ホームページを作りたいけど、誰に頼めばいいのか分からない…」そんなお悩み、ありませんか?
Web制作を外注するとき、制作会社とフリーランスのどちらに依頼すべきかで迷う方は非常に多く、間違った選択が「思ったような成果が出ない…」「イメージと違うサイトになった…」といった後悔につながることも。
Web制作を初めて外注する方や、何から始めてよいか分からない初心者の方に向けて、「目的別にどちらが最適なのか」「予算や納期、サポート体制の違い」「信頼できる相手の見つけ方」までを、制作のプロの視点から分かりやすく解説しています。
また、「まずは自分でやってみたい」という方に向けて、ノーコードツールを使ったセルフ制作の可能性にも触れています。
① Web制作を外注する前に知っておきたい“前提知識”
ホームページを作ろうと考えたとき、多くの方がまず直面するのが「誰に頼めばいいのか分からない」という悩みです。
制作会社に依頼するのが良いのか、それともフリーランスに頼むのが良いのか。
その選択は、あなたの目的や予算、運用スタイルによって大きく変わってきます。
しかしその前に、そもそも「なぜWeb制作を外注したいのか」「どんなサイトをつくりたいのか」について、少し立ち止まって考えてみることが重要です。
目的がはっきりしないまま外注先を選ぶと、完成したあとに「イメージと違った」「成果につながらない」と感じることもあるかもしれません。
依頼前に明確にしておくべき3つの視点
【自分にとっての「目的」を明確にする】
- 集客が目的なのか、名刺代わりにしたいのか
- ネットショップをやりたいのか、予約受付をしたいのか
- 「なんとなく必要そう」ではなく、何を得たいかを考える
【更新や運用にどれくらい関われるかを整理する】
- 日々の更新を自分でやる予定なのか、丸投げしたいのか
- 月に何度くらい更新するかなど、想定してみる
- 操作が難しければ、CMS(WordPressなど)を入れることも視野に入れる
【使える予算と納期の目安を考えておく】
- 「いくらまでなら出せるか」をざっくりでよいので把握する
- 納期に余裕があるか、急ぎなのかで選択肢も変わる
② 制作会社とフリーランス、それぞれの特徴と強み
依頼先を選ぶときに最も迷いやすいのが、「制作会社に頼むべきか、フリーランスに頼むべきか」という点です。
それぞれに明確なメリットと注意点があり、どちらが正解というわけではありません。
たとえば、制作会社はチームで動いているため、デザイン・コーディング・SEO・保守など各分野のプロが対応してくれる安心感があります。
一方で、フリーランスは直接やりとりができ、柔軟で価格も抑えやすいという魅力があります。
あなたの「やりたいこと」「求めるスピード感」「相談したいスタイル」によって、向いている依頼先は変わってきます。
自分の状況にあわせた選択を
【制作会社の特徴と向いているケース】
- チーム対応で専門性が高く、クオリティの安定感がある
- 企業サイト、大規模サイト、ブランド重視の案件に強い
- 問い合わせやサポート対応がしっかりしている
【フリーランスの特徴と向いているケース】
- 価格が抑えられやすく、やりとりがスムーズ
- 個人事業主、店舗オーナー、初めての方でも相談しやすい
- 提案力や柔軟性があるが、スケジュールの把握は必要
【両者を比べる際に見るべき視点】
- 実績やポートフォリオを確認する(過去の制作事例)
- コミュニケーションの取りやすさや返信スピード
- 納期や保守管理、SEO対応など、依頼後の体制も確認
③ 判断のポイント①:目的とゴールの一致を見る
Web制作を外注する最大の目的は、「自分ではできない部分をプロに任せること」です。
ただし、目的が曖昧なまま依頼すると、どんなに技術力の高い相手でも、納得のいく仕上がりにはなりにくくなります。
ここで大切なのは、「制作会社やフリーランスが、自分の目的をどれだけ理解し、共に考えてくれるか」という視点です。
ただ作るだけでなく、「一緒に考えてくれるかどうか」こそが、判断の大きな基準になります。
自分のゴールと相手の視点が合っているか確認する
【目的と提案内容が合っているか】
- ヒアリングの段階で、こちらの要望を汲み取っているか
- 「集客したい」ならSEO提案、「ブランド重視」ならデザイン提案など
【ただ作るだけでなく、成果まで見てくれるか】
- 公開後の運用まで考慮した提案かどうか
- 「どうすれば成果につながるか」を一緒に考えてくれるか
【打ち合わせ時の“質問の質”に注目】
- 「なぜ作るのか」「誰がターゲットか」など、深掘りしてくれるか
- こちらの考えを否定せず、整理してくれるスタンスかどうか
④ 判断のポイント②:予算とコスト感覚の違いを理解する
「Web制作にはどれくらいの費用がかかるの?」という疑問は、多くの方が最初に抱くものです。
ここでのポイントは、単に金額の「高い・安い」で判断するのではなく、「何にコストがかかっているのか」を理解することです。
制作会社とフリーランスでは、料金体系やコスト構造に違いがあります。
制作会社は人件費・運営費・チーム体制がある分、価格が高めに設定されています。
その分、複数人でのチェック体制や品質保証、サポート体制が整っています。
一方、フリーランスは一人で行う分、価格を抑えやすいですが、そのぶん一つひとつの作業が属人的である点もあります。
大切なのは、予算内で「自分の目的を叶える」方法を一緒に考えてくれる相手かどうか、です。
金額だけでなく“中身”を見て判断する
【制作会社のコスト構造】
- ディレクター・デザイナー・エンジニアなど複数人が関わる
- 社内のチェック体制・保証が価格に含まれている
- 運用費や保守料金も別途かかることが多い
【フリーランスのコスト構造】
- 人件費や中間コストがない分、予算を抑えやすい
- 作業は一人で行うため、スピードや品質は実力に依存する
- 案件によって料金が変動しやすい(パッケージ化されていないことも)
【見積もりを見るときのチェックポイント】
- 「何にいくらかかっているか」の内訳が明確か
- 「打ち合わせ」「提案書」「画像加工」「保守」などは含まれているか
- 「総額いくら」ではなく、何に価値を感じるかを軸に判断する
⑤ 判断のポイント③:納期と柔軟性の違いを把握する
Web制作には、必ず「スケジュール」が伴います。
たとえば「1ヶ月後のイベントに間に合わせたい」「できるだけ早く公開したい」など、納期は依頼する側にとって大きな判断材料になります。
制作会社は、チームで作業するため納期のコントロールがしやすく、トラブル時にも代替要員を確保しやすいメリットがあります。
一方、フリーランスは柔軟性が高く、「ちょっとこの文言を変えてほしい」といった細かい変更にも迅速に対応してくれることが多いです。
ただし、スケジュールはその人の稼働状況に大きく左右されるため、確認は必須です。
納期感覚とレスポンス力も選択の鍵
【制作会社の納期感覚】
- 事前にスケジュール表を共有されるケースが多い
- スケジュールに沿った進行で、計画性重視
- 担当者が変わることもあるため、伝達の時間が必要
【フリーランスの納期感覚】
- 個人で管理しているため、相談次第で融通が利くことも
- 夜間・土日対応してくれるケースもある(要確認)
- 一方で体調不良やトラブル時のリスクもある
【確認しておきたい柔軟性のチェックポイント】
- 「対応できる時間帯」や「リードタイム」を事前に共有しておく
- 修正依頼へのスピードや回数について合意を取る
- 「公開日」から逆算して、無理のない進行計画を立ててもらう
⑥ 判断のポイント④:アフターサポートと運用体制の違い
Webサイトは、公開して終わりではありません。
更新や修正、セキュリティ対応、アクセス解析など「運用」に関するサポートが必要になる場面は必ず出てきます。
制作会社はこの「保守・運用」までをサービスとして提供しているケースが多く、定額制で安定したサポートが受けられるのが特徴です。
一方で、フリーランスの場合は「都度対応」が多く、柔軟な対応を受けられる一方で、長期的なサポート体制は個々のスキルや意識に依存します。
運用に不安がある方は、「公開後も寄り添ってくれるかどうか」を大きな判断基準にしてみましょう。
「公開後」の支援内容を事前に確認する
【制作会社の運用体制】
- 保守契約により、月々の更新・修正・監視などを代行してくれる
- トラブル時にも早期対応してくれる体制が整っている
- 内容が「パッケージ化」されており、安心感がある
【フリーランスのサポートスタイル】
- 運用や保守は「希望すれば対応」スタイルが多い
- 小規模事業者・個人向けに柔軟に対応してくれることも
- 連絡手段(LINE、メール、チャットなど)も事前に確認を
【公開後に意識したいポイント】
- 「更新は自分でできるか、それとも依頼したいか」
- 「何かあったとき、すぐに相談できる人がいるか」
- 「保守・セキュリティ・SEOチェック」なども含めて考える
⑦ 判断のポイント⑤:「信頼できる人」に出会えるかどうか
ここまで、目的・予算・納期・運用体制といった「条件面」での判断基準をお伝えしてきました。
しかし、最終的に大切なのは「この人(この会社)にお願いしたい」と思えるかどうかです。
制作物の完成度はもちろん大切ですが、それ以上に「気持ちよくやりとりできるか」「こちらの話をしっかり聞いてくれるか」という人間関係の部分が、プロジェクト全体の満足度を大きく左右します。
Web制作は、短くても1〜2ヶ月、長ければ半年以上にわたるやりとりが続くものです。
相性や信頼感は、後々の「細かな修正」や「相談したいとき」に大きな差となって現れます。
「この人と進めたい」と思えるかを大切にする
【打ち合わせで見るべき“人柄”のポイント】
- こちらの話をよく聞いてくれるか(傾聴力)
- 分かりやすい言葉で説明してくれるか(専門用語をかみ砕いてくれる)
- 無理に契約を迫ってこないか(誠実な対応か)
【信頼感が持てるかを見極める質問例】
- 「納品後はどんなサポートがありますか?」
- 「予算内で何ができますか?」
- 「初心者なので不安があるのですが、大丈夫ですか?」
【“人で選ぶ”という判断も立派な基準】
- 肩書きよりも、対応力や相性を重視してみる
- ポートフォリオ以上に、やりとりの中で安心感があるかを感じてみる
- 選ぶこと自体も「共同作業の第一歩」だと考えるとよい
⑧ 実は自分でもできる?セルフ制作という選択肢
「制作会社に頼むのは不安」「フリーランスを探すのが大変」「予算がない」
そんなとき、実は選択肢のひとつとして「自分でホームページを作ってみる」ことも可能です。
制作会社の私が言うと元も子もありませんが…。
最近では、ノーコードツール(HTMLやCSSを書かずに作れるツール)も進化しており、WixやSTUDIO、ペライチ、WordPressなどを使えば、ある程度のサイトであれば個人でも作成できます。
もちろん、クオリティや自由度には限界がありますが、「一度試してみる」「とりあえず仮のサイトを作っておく」ことで、外注時のイメージも明確になります。
まずは触ってみることで理解が深まる
【初心者におすすめのツール】
- Wix:直感的な操作で誰でも簡単にサイトが作れる
- STUDIO:デザイン性が高く、ポートフォリオやブランドサイトに向いている
- WordPress(テーマ使用):情報発信やSEO対策に強く、将来的な拡張性もあり
【自分で作ることのメリット】
- コストを抑えられる
- 運用や更新の仕組みが理解できる
- 外注時に「何ができて、何が難しいのか」を伝えやすくなる
【こんな方にはおすすめ】
- 情報量が少ない/1ページだけ作りたい
- 時間がある程度とれる/学ぶ意欲がある
- まずはトライしてみて、将来的に外注を検討したい
⑨ まとめ:どんな選択でも、正解にしていける
ここまで、Web制作を外注する際の判断基準について、制作会社・フリーランス・セルフ制作という三つの視点からお伝えしてきました。どの選択にもメリットと注意点があり、「絶対的な正解」はありません。
大切なのは、自分にとって「ちょうどいい選択」を見つけていくこと。
そして、決断した後に「よし、やってみよう」と動き出すことです。
悩む時間は決してムダではありません。
それは「どうすればより良いものになるか」と真剣に考えている証拠です。
Webサイトは、あなたの思いやサービスを届ける“デジタルの名刺”であり、“営業マン”でもあります。
だからこそ、誰と一緒につくるか、自分でつくってみるのか、その選択は未来への第一歩になります。
最後に、あなたの選択を応援する視点を
【迷ったときは、こんな考え方もおすすめ】
- 「話していて安心する相手」を選ぶ
- 「納得できる説明」がある方を選ぶ
- 「無理なく一歩を踏み出せそう」と感じる選択肢を選ぶ